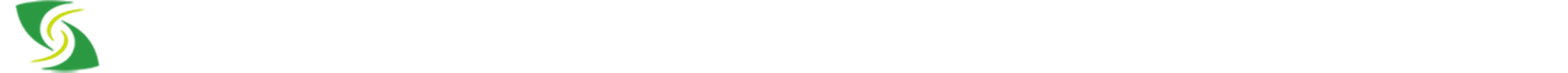教員紹介
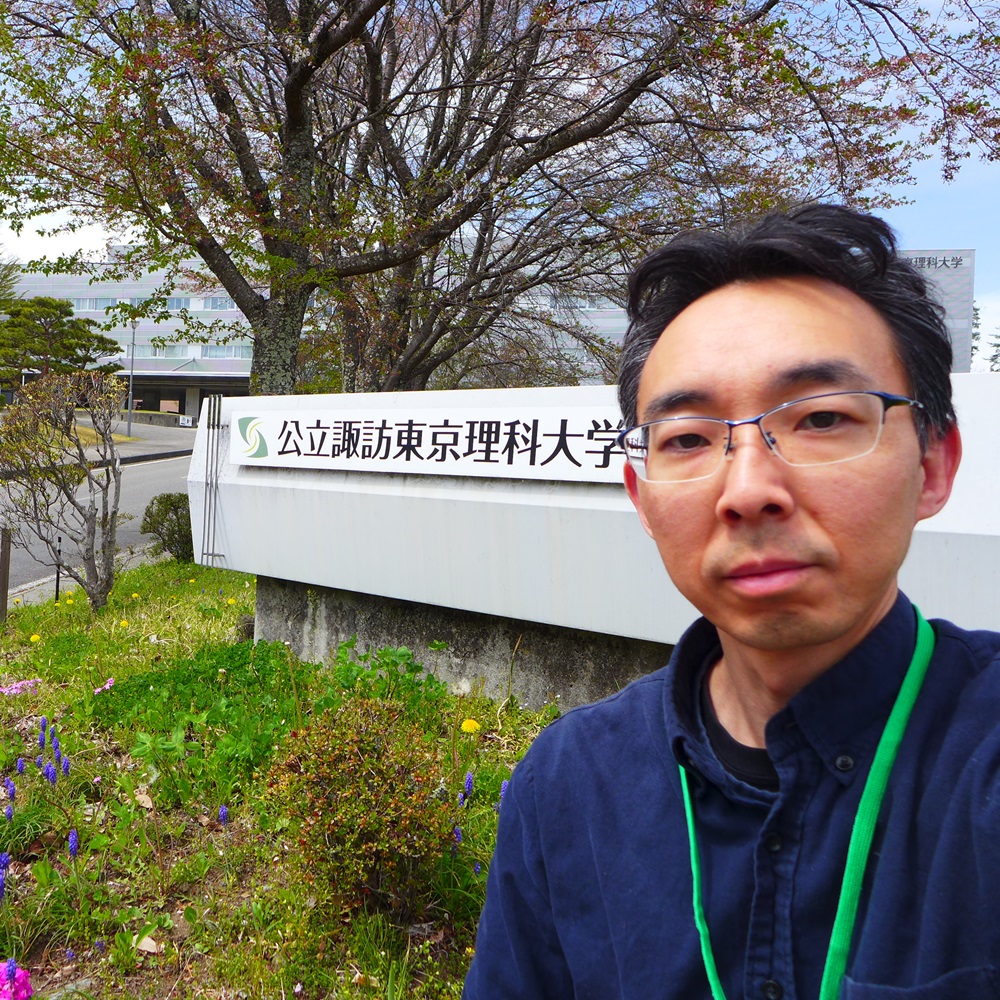 |
|
|---|---|
| 経 歴 |
|
| ひとこと |
天文学者・荒木俊馬先生が開学した京都産業大学で物理学と天文学の基礎を学び、大阪府立大学大学院で日本を代表する電波望遠鏡用受信機の研究者である小川英夫先生に師事。宇宙電波天文学を専攻して、東大60cm電波望遠鏡(のちの"あまのがわ望遠鏡")の開発で修士号、野辺山45m電波望遠鏡で世界初の両偏波・両サイドバンド受信機システムの実用化に成功し博士号を取得しました。 その後、国立天文台野辺山宇宙電波観測所と東京大学天文学教育研究センターで4年少々のポスドクを経験。超伝導受信機の開発は続けつつ、Active galactic nucleus(AGN)やスターバースト銀河核のような特に活動的な銀河の化学状態の解明をテーマとし、これまでに自分が開発した装置を(自分で)使って、本格的な観測的研究(サイエンス)に取り組みました(いま流行りの言葉で言うと "二刀流" ?)。 2012年に名古屋大学太陽地球環境研究所(2015年に宇宙地球環境研究所に改組)に助教として着任。太陽地球系科学分野で、主にミリ波帯大気ラジオメータ開発と中層大気・極域大気の科学研究に従事する傍ら、大学院工学研究科電子情報システム専攻(2017年より電気工学専攻)で学生の教育を13年間担当しました。 2025年、長野県にある公立諏訪東京理科大学に准教授として着任し、高周波の電波領域であるテラヘルツ波帯技術の開拓と新規デバイス開発、宇宙観測・地球観測装置へのシステム応用、そして世界の電波望遠鏡を用いて宇宙の謎に挑む観測的研究の三本柱をテーマとする新しい研究室をスタートさせました。 また研究に関しては、小学生のころから興味がある「宇宙(星を見ること)」と「電波(アマチュア無線をやっていました)」が常に基軸のテーマではありますが、星形成過程、銀河面サーベイ、銀河の活動性、超巨大ブラックホール、星間化学、彗星や流星、地球大気(オゾン層)、超伝導検出器、導波管回路、電波望遠鏡システム、地球大気ラジオメータ、流星レーダー、ダークマター探索…と、宇宙科学・地球科学・環境学・電波工学と、興味の赴くままに広い領域に渡って活動を行ってきました。 これまでのこのような経験を生かすことで、一つの特定の分野・視点・慣習に囚われず、常に新たなものを想像・創造し、学際的・融合的な研究によって人類社会に貢献する成果を得ること、そしてそのような多角的な視点を持つ次世代の研究人材を育てていくことを心掛けています。今後とも、どうぞよろしくお願い致します。 |